人前でお茶を立てる2回目と3回目の機会を得ました。
今回参加させていただいたのは「月釜」という行事です。
先生がホスト(亭主)となって茶会を主催するイベントで4回の席を設けることとなっていました。
このうち2回を担当させていただくことになったのです。
デビュー戦を振り返る
はじめて人前でお茶を立てたのは、3月末の利休忌のとき。
38歳にして人生で初めての発表会。
それはもうみっともないほどにガチガチに緊張して、普段なら絶対にやらかさないミスを連発。
焼けた茶釜のつまみを素手で持つ私お得意の根性焼きを披露して見せ場を作る、という忘れられない一席となりました。笑
続き薄
今回の月釜では「続き薄」というお手前をさせてもらいました。
通常の茶席では濃茶を出した後に、席を改めて薄茶をどうぞ、となるところ、濃茶が終わったらそのまま続けて薄茶を差し上げるというお手前です。
濃茶と薄茶と2服点てるために所要時間も長く、正座する時間も長く、足が痺れる恐れも高い。
利休忌の時の「運びの濃茶」より一層複雑でチャレンジングなお手前です。
そのため、利休忌が終わってからの通常の稽古は全て「続き薄」のお稽古をさせてもらい、和服を着てのお稽古も含めて、できることを全てやってから本番に挑みました。
違うものが見えてきた
結果的には「続き薄、それ自体」は多少のミスこそあれ、なんとかやってのけることができたと思います。
いくつかの小さなミスは素知らぬ顔をしてやり過ごすというハッタリをかますこともできました。笑
想定通り足は痺れ(笑)2回目の席はすぐに立ち上がる事ができず、みっともない姿を晒してしまいました。
とはいえこの程度のことは織り込み済みなので、どうという事もありません。
こういう受け止めができるようになったのは、経験値のおかげとしか言いようがありません。
でも、こういった心のゆとりが出てきて、前回には全く見えなかったものがハッキリとわかりました。
それは水屋、すなわち裏方での仕事力です。
「水屋」という新たな地平
1回の席に30人ほどのお客さんが入る茶会では、お手前をする人は正客(メインゲスト)1名分のお茶を立てるだけです。
他の29人の分はどうするのかというと、裏方(=水屋)に控えたお手伝いさんたちが準備をするのです。
水屋からは直接茶席の様子を伺うことができません。
襖越しに聞こえてくる僅かな音や、数ミリの襖の隙間から見える僅かな様子を伺い、大勢のお客さんたちにお茶やお菓子を出すタイミングを見計います。
これには並々ならぬ相当なスキルが要求されます。
まず、全体の流れを把握している必要があります。その上で、どのタイミングで何を出すべきかを瞬時に決断しなければなりません。この決断を視覚情報なしで行うのです。これはハイレベルな知識に加えて、状況判断能力と決断力が求められる高等技術です。
お茶会を主催する豊富な経験がなければ、まず不可能。
さらに「次客の茶碗を引き忘れた」とか「途中で客が1名増えた」とかイレギュラーが常に発生するので、その状況を認めた人が瞬時に情報を共有し、その都度、臨機応変に即断即決。
水屋にいる全員がその能力を求められるのです。
もちろん全員がこの能力を十分に発揮しているとは言えません。私のように指示がなければ何をして良いかわからない人もいれば、自分のポジションを固めてそこ以外の仕事をしないと徹する人もいます。
では私がどうなりたいのかというと、いうまでもありません。
即断即決、臨機応変に快刀乱麻のごとく手足と心を働かして、それでいて頭と心は冷静沈着。水屋の必殺仕事人になりたいと思います。
日々是修行
そうなるためにはどうしたらいいかと考えてみますと、これは茶席に限らず日々の訓練ができることだと思いました。
日々の仕事でも良いですし、暮らしの営みでも良いです。
全体像を把握して、プロセスの啓示的進行を読みながら、物事がスムーズに運ぶように段取りをする。
合間合間に挟まるイレギュラーを、その都度臨機応変に対処して軌道を修正する。
自ら動いて事をなし、時には人を動かし事をなす。自他にこだわらず、最善の一手を打つ。
このようにできるようになることが、水屋の仕事にきっと通じるはず。
ただお手前ができるレベルは言われた通りのことをこなすレベルであったのかも…と思うと呆然としてしまう感もありますが、これがお茶の面白いところであるとも思います。
決してゴールに至ることはない、これぞ道。
ぼくの草履
ちなみに、会場についたら自らの草履は水屋の方に下げておくのがルールだったようなのですが、初参加の私はそれを知らず。
他の水屋手伝いの方々が自分の草履を持って水屋に下がるのをみて、慌てて自分の草履を見に行きましたが、そこに自分の草履はありませんでした。
どこにいったのかと探す間も無く、ある人が「ぼくの分も下げておいたよ❤︎」と私に向かってにっこり微笑んで仰るではありませんか。
二人称として「ぼく」と呼ばれるなんて…
まだまだ、全く修行が足りません。
真ん中を歩く
最後に、今回の続き薄で自画自賛ながら良かったと思うのが「畳の真ん中を歩く」「畳の真ん中を基準とする」という意識。
何にしても、真ん中を意識すること、中心を意識することによって、お手前や体さばきの中に1つの基準軸ができます。
中心に沿えるか沿えないかで、都度お手前の良し悪しのジャッジができるようになったことはお点前をする上で良かったです。
ピッタリ中心にいると自覚できた時は「ヨシ!」という安心感をともなって自信を持ってお手前ができますし、外れている場合は「いかんいかん」と気持ちを改めることができました。
月釜を終えて思うのは、やればやるほどお茶の道の果てしなさと素晴らしさが広がり、深まってゆくということです。
これからも多くの経験にチャレンジしてゆきたいと思います。
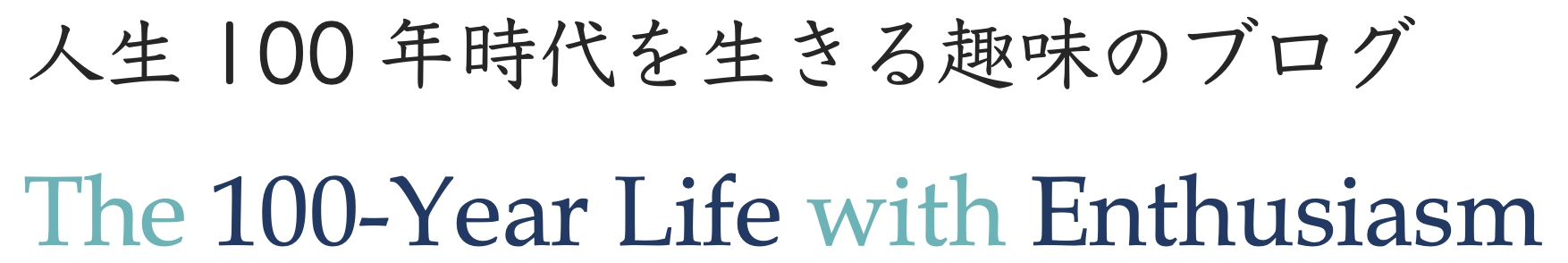



コメント